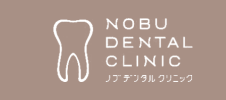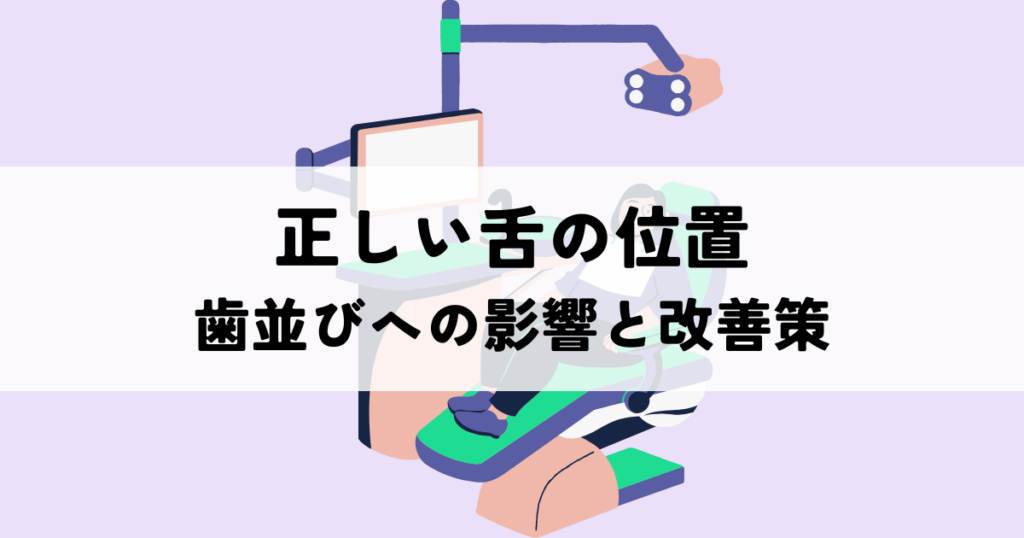歯並びの悪さに悩んでいませんか?
もしかしたら、その原因は舌の位置にあるかもしれません。
普段意識することのない舌の位置ですが、実は歯並びや口元の健康に大きな影響を与えています。
今回は、正しい舌の位置と歯並びの関係性、セルフチェック方法、そして改善のためのトレーニング方法についてご紹介します。
正しい舌の位置を身につけ、美しい歯並びと健康的な口腔環境を目指しましょう。
舌の位置と歯並びの関係を理解する
正しい舌の位置とは?セルフチェック方法
正しい舌の位置は、舌の先が上の前歯の付け根にある「スポット」と呼ばれる部分に触れ、舌全体が上顎にくっついている状態です。
唾を飲み込む時、舌の先がスポットから離れて歯に触れてしまう場合は、舌の位置が正しくない可能性があります。
鏡を見ながら唾を飲み込む動作を確認したり、チューイングガムを使って舌の形状を確認したりすることで、セルフチェックを行うことができます。
ガムを舌の上で丸め、上顎に押し当てた際に、綺麗に丸くならない、前歯に触れる、縦長になるなど、形状に問題があれば舌の位置の改善が必要かもしれません。
舌の位置が歯並びに与える影響
舌の位置が正しくない状態、特に舌が下にある「低舌位」は、歯並びに悪影響を及ぼします。
一日に何度も繰り返される飲み込みの動作で、舌が歯を圧迫することで、「出っ歯」「受け口」「開咬」などの不正咬合を引き起こす可能性があります。
また、低舌位は口呼吸を招きやすく、口の中の乾燥や、虫歯・歯周病リスクの増加にも繋がります。
さらに、発音にも影響し、サ行、タ行、ナ行、ラ行などの発音が不明瞭になる可能性も。
低舌位と関連する口腔内の問題
低舌位は、歯並びの問題以外にも、様々な口腔内の問題と関連しています。
例えば、口呼吸による口内の乾燥、虫歯や歯周病のリスク増加、口臭、そして睡眠時無呼吸症候群などの可能性も指摘されています。
また、舌の側面に歯型が付いている、口が常に開いている、声が小さい、滑舌が悪い、食事中にクチャクチャ音を立てる、いびきをかくといった症状は、低舌位を示唆する可能性があります。

舌の位置と歯並びの改善策
効果的な舌癖改善トレーニング
舌の位置を改善するためには、継続的なトレーニングが不可欠です。
「あいうべ体操」や「ポッピング」といった、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングが効果的です。
「あいうべ体操」は、「あ」「い」「う」「べ」と口を大きく動かすことで口周りの筋肉を鍛え、「ポッピング」は舌を上顎に吸着させ、音を立てることで舌の筋肉を強化します。
その他、舌を様々な形に変えたり、箸を使って舌を鍛えるトレーニングなども有効です。
これらのトレーニングは、鏡を見ながら行うことで、舌の位置や動きを確認しながら行うことができます。
口腔筋機能療法(MFT)について
口腔筋機能療法(MFT)は、口周りの筋肉の機能を改善することで、舌の位置や飲み込み方、発音などを改善する治療法です。
専門家の指導の下、適切なトレーニングを行うことで、歯並びの改善や、口呼吸の改善、そして発音の改善にも繋がることがあります。
MFTは、歯列矯正治療と併用することで、治療効果を高め、後戻りを防ぐ効果も期待できます。
歯列矯正との連携
歯列矯正治療は、歯並びを改善するための有効な手段です。
しかし、舌の位置が正しくないまま矯正治療を行うと、治療後の後戻りや、治療効果の低下に繋がる可能性があります。
そのため、歯列矯正治療を受ける際には、舌の位置の改善も同時に行うことが重要です。
MFTと歯列矯正を組み合わせることで、より効果的な治療を行うことができます。
特に、開咬などの治療においては、舌癖の改善が治療の成功に大きく影響します。
矯正装置を用いて舌が歯に触れないようにすることで、歯並びの改善を促すことも可能です。
まとめ
舌の位置は、歯並びや口腔内の健康に大きな影響を与えます。
正しい舌の位置をセルフチェックし、必要に応じて舌癖改善トレーニングやMFT、専門家への相談などを検討しましょう。
継続的な努力によって、美しい歯並びと健康的な口腔環境を実現できます。
口周りの筋肉を鍛えるトレーニングを継続的に行い、正しい飲み込み方を意識することで、歯並びの改善だけでなく、口呼吸や発音の問題の改善も期待できます。
専門家と連携することで、より効果的な改善策を見つけることができるでしょう。
歯並びに不安がある方は、早めに歯科医に相談することをお勧めします。